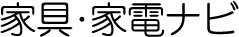遺品供養は必要なのか? 処分する方法や依頼先などをチェックしよう!
1.遺品供養とは?
まずは、遺品供養とはどのようなことなのか、基本情報をチェックしておきましょう。
1-1.遺品に宿っている魂を抜くこと
簡単に説明すると、遺品供養とは遺品に宿っている魂を抜くことです。遺品の中には故人の魂が入っているものもあり、それらをそのまま処分するのはよろしくないといわれています。遺品に宿っている魂を抜いてから処分することで、遺品や故人に対してきちんと敬意を払えるというわけです。
つまり、遺品供養は感謝を込めて遺品を供養し、故人を偲(しの)ぶ大切な作業といえるでしょう。後ほど【4.遺品供養を依頼するには?】でも詳しく説明しますが、供養には自宅まで訪問してくれる現場供養とほかの遺品と合同で行う合同供養の種類があります。
1-2.お寺や神社で行われるお焚(た)き上げ
遺品供養には、お寺や神社で行われるお炊き上げがあります。お炊き上げとは、故人が大切にしていたものを焼却し浄火することです。ただ、遺品を焼くだけではありません。お寺や神社といった神聖な場所で感謝を込めて焼却し浄化するのが大きなポイントとなります。
浄火することで故人の魂を天に送り供養できるというわけです。日本は昔から仏壇など粗末に扱えないものに対してお焚き上げを行ってきましたが、現在では手帳・写真・寝具類と焼却できるものであればお焚き上げの対象となっています。
2.遺品供養は必要なのか?
遺品供養は本当に必要なことなのか、その理由について説明します。
2-1.なるべく遺品供養は行うべき
遺品供養は絶対にしなければならないわけではありませんが、なるべく行ったほうがいいといわれています。その理由はさまざまですが、1番の理由は故人を偲ぶことにつながるからです。前述したように、故人の魂が入っているものを抜いてから処分するのが遺品供養の目的となります。
遺品供養をせずに処分してしまうと、故人の魂が入ったまま捨てることになるので故人に対して罪悪感を覚えてしまうでしょう。大切な人の遺品ならなおさら、きちんと供養してから手放すべきです。
2-2.遺族の気持ちが楽になる
遺品供養は故人を偲ぶことにつながるだけでなく、遺族の気持ちも楽になります。大切な人が亡くなると気持ちに整理がつかなくなりますし、できるだけ遺品を残しておきたい思いが強くなるでしょう。
けれども、すべての遺品を手元に残すことはできません。だからこそ、感謝の気持ちを込めて遺品供養を多なうことで、遺品に対する思いも整理できます。なかなか手放すことができなかった遺品でも供養を行えば、気持ちを楽にして手放せるようになるでしょう。遺族の気持ちを整理するためにも遺品供養はとても大切な意味があります。
2-3.たたりやバチなどの不安から解消される
本当に遺品供養は必要なのか疑問に感じている方は多いと思いますが、少しでも不安要素があるならきちんと遺品供養をしたほうがいいでしょう。日本は昔から魂が宿っているものは供養をしてから処分する習慣がありました。遺品供養にはお祓いのほか、悪い縁を切るという意味も含まれています。
遺品供養をせずに処分する=たたりやバチがあたるという考え方があるので、きちんと供養してから処分すべきでしょう。ただし、宗派・浄土真宗には魂入れ・魂抜きの概念がないため、供養は必要ないという考えを持っている方もいます。つまり、遺品供養は故人や遺族の考え方によって異なるでしょう。